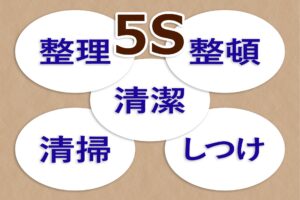はかり検定は受検しなければならないの?
はかり検定のスケジュールや事前に準備する物を知りたい
このようにはかり検定について詳しく知りたいと思っている方は、多いのではないでしょうか。
はかり検定は、取引や証明に使用するはかりが適正であることを証明するために受検が必要な試験です。近年、新たに自動はかりも検定の対象となり、既存の自動はかりについても今後、検定を受ける必要があります。
導入前に、必要な手続きや検定費用、更新のタイミングなどを確認し、適正に運用できるよう準備しましょう。
そこでこの記事では、はかり検定の概要やスケジュール、事前に準備しておくことについて解説します。以下の記事では、組み合わせはかりのメーカーについて紹介しているので参考にしてください。
はかりの検定義務化とは
取引に組み合わせはかりなどのはかりを使用する際は、はかり検定を受ける必要があります。この検定が導入された目的は、正確な計量を確保し、消費者を保護することにあります。
食品の表示や取引には、正確な重量が求められます。不正な計量が行われると、消費者に不利益をもたらすだけでなく、企業の信用にも大きな影響を及ぼします。
計量制度の見直しにより、自動はかりが特定計量器に分類されることになったため、取引で自動の組み合わせはかりを使用している場合、検定の対象となります。具体的には、ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかりの4種類が該当します。
なお、ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケールについては、はかり検定の開始日が2028年4月以降に延長されています。導入を検討する際は、検定の適用時期を確認し、計画的に準備を進めましょう。
検定制度の概要とスケジュール
組み合わせはかりや自動計量器などのはかりを導入する際は、検定制度の概要とスケジュールをチェックしておく必要があります。
検定の種類や実施期間、検定有効期間を把握しておくことで、検定の受け漏れを防げます。
検定の種類
自動はかりの検定対象になるのは、現時点では自動捕捉式はかりの 1種類のみです。次の3つの条件をすべて満たす場合、はかり検定を受ける必要があります。
- 取引または証明に使用している
- 目量が10mg以上、目盛標識数が100以上である
- ひょう量が5kg未満である
上記のいずれか 1つでも満たさない場合は、はかり検定の対象外となります。
検定の時期について
・2024年3月31日までに 検定を受けずに取引または証明に使用していた場合
→ 検定対象の 「既に使用しているはかり」 に該当
・2024年3月31日までに 検定を受けていた場合
→ 検定対象の 「新たに使用するはかり」 に該当
検定が必要かどうかを確認し、必要な場合は適切なタイミングで受検しましょう。
また、「組み合わせはかり」は現時点では、はかり検定の対象とはなりません。ただし、今後の法改正や使用環境によって適用範囲が変わる可能性もあるため、導入時には最新の計量法規制を確認することをおすすめします。
検定有効期間
はかり検定の 有効期間は通常2年間です。そのため、検定対象のはかりを使用する場合は、2年ごとに検定を受ける必要があります。
ただし、適正計量管理事業所に届出を提出した場合は、有効期間が6年間 となります。
有効期間の計算方法
・検定の有効期間の開始日 は、検定に合格した翌年の4月1日 です。
・有効期間が終了する1年前から、次回の検定を受けることが可能です。
検定の有効期限を正しく把握し、適切なタイミングで更新手続きを行いましょう。
検定対応に必要な準備事項
はかり検定を受ける際は、事前に下記の準備が必要になります。
検定依頼の申し込み
検定器物の情報を「検定依頼書」に記載して検定機関(指定検定機関)に提出します。その際に必要となる資料としては、仕様書、銘板情報、製品の使用計量範囲、試験サンプルの準備有無となります。
検定手数料
はかり検定を受けるには検定手数料が必要です。検定手数料は受講するメーカーや機関、ひょう量によって異なりますが、40,000〜70,000円ほどになります。
また、営業日の所定時間外や深夜、休業日などは検定手数料が割増されるケースが多いです。検定手数料とは別途で検定員の交通費も求められるため、検定手数料に関しては、検定機関に見積依頼をすることをお勧めします。
その他
その他の準備事項として、製造メーカーへ連絡して検定前に事前点検やメンテナンスを受けて交換部品の有無を確認することも必要です(既に使用しているはかりは老朽化により検定に合格しない場合があります)。
事前に必要書類を確認し、不足や漏れがないように準備を進めましょう。
検定実施時の注意点
はかり検定実施時の注意点は以下の3つです。
3つの注意点を把握しておくことで、はかり検定がスムーズにできるでしょう。
検定準備をしておく
はかり検定を実施する前に、しっかりと準備を整えましょう。
検定をスムーズに進めるために、製造メーカーへ連絡して検定前の事前点検やメンテナンスを受けて交換部品の有無を確認することも必要です(既に使用しているはかりは老朽化により検定に合格しない場合があります)。
検定を実施するための作業スペースも確保しておくことが重要です。
検定当日の流れの確認
検定を実施する前に、当日の流れを事前に把握しておきましょう。事前に流れを理解しておくことで、検定にかかる時間の目安がわかり、スムーズに対応できます。
検定当日は、申請者が立ち会う必要があります。検定では以下の項目が確認されます。
・器差(自動重量選別機:平均器差、それ以外:個々の器差)
・表記の確認
・最大許容標準偏差(自動重量選別機のみ)
・動作補正の範囲
・ゼロ点設定精度
・風袋引き装置の精度
・偏置荷重の影響
・平衡安定性(静的計量はかりのみ)
・表示装置および印字装置の一致
新規に導入するはかりについては、上記すべての項目が検査対象となります。一方で、既存の機器の検定では、「器差」「表記」「最大許容標準偏差」「ゼロ点設定精度」の4項目のみがチェックされます。
よくあるトラブルの事前把握
検定を円滑に進めるためには、事前に想定されるトラブルを把握しておくことが重要です。特に、検定当日に機器が正常に動作しないケースがよく発生します。
自動はかりは精密機器であるため、検定当日に普段通りの動作をしない可能性があります。これを防ぐためにも、事前にメンテナンスや動作確認を徹底しておきましょう。
また、はかり検定は公正に実施されますが、稀に基準を満たしているにもかかわらず不合格と判断されることがあります。その場合は、不合格の理由を詳しく説明してもらい、必要に応じて検定員やメーカー、認定機関に異議申し立てを行うことも検討しましょう。
大和製衡のはかりなら安心して導入可能

| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 大和製衡株式会社 |
| 所在地 | 兵庫県明石市茶園場町5-22 |
| 創業年月 | 大正9年2月(西暦1920年) |
| 公式サイト | https://www.yamato-scale.co.jp/ |