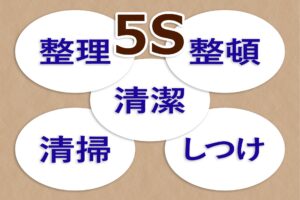製造業において、廃棄物の発生は避けがたい課題ですが、実はその見直しこそが大きなコスト削減につながる可能性を秘めています。廃棄物の量を減らすことで、処理費用や原材料のロスを抑えられるだけでなく、作業効率の改善や品質向上にもつながり、利益率の向上が期待できます。
本記事では、製造現場における廃棄物削減の手法やメリットについてわかりやすく解説します。現場のコストを削減したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
また、以下ではおすすめの組み合わせはかりメーカーについて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
廃棄物の処理コストの内訳

製造現場で発生する廃棄物の処理には、さまざまなコストがかかっています。具体的には、以下の内訳です。
それぞれの処理コストについて解説していきます。
収集・運搬費

収集・運搬費は、廃棄物を製造現場から処理施設まで運ぶために必要な費用です。一般的には、廃棄物の種類や量、運搬距離によって費用が決まり、定期的な回収契約を結んでいる場合もあります。特に重量物や危険物、特殊な管理が必要な廃棄物は、一般的な産業廃棄物よりも高額になります。
また、容器のサイズや積載効率によっても運搬回数が変わるため、コストの変動要因です。仮に廃棄物が適切に分別されず混在している場合、処理業者は追加対応を求められるため、余計なコストが発生することもあります。
収集・運搬費を削減するには、廃棄物の発生源である現場レベルでの適切な分別や、圧縮処理、積載効率の見直しが有効です。
処分費

処分費とは、廃棄物を最終的に焼却・埋立・脱水などの方法で処理するためにかかる費用です。処理方法や廃棄物の性質によって単価が異なり、一般廃棄物よりも産業廃棄物のほうが費用が高額になる傾向にあります。
特に、含水率が高い廃棄物や有害成分を含む廃棄物は、処理に手間がかかるため高コスト化しやすいです。
処分費は一度契約すると継続的に発生する固定費となるため、削減効果が長期的に利益へ直結します。コストを見直す上では、廃棄物がどのような処分方法を経ているのかを把握し、削減可能な工程や性質の見直しを図ることが重要です。
中間処理費・再資源化費

中間処理費は、廃棄物を再資源化や最終処分する前に粉砕・選別・脱水などの中間工程を行う際に発生する費用です。再資源化費は、資源として再利用するために必要な加工や処理にかかる費用を指します。これらのコストは、廃棄物の性質や分別状況、再資源化の難易度により変動します。
例えば、分別が不十分なまま排出された廃棄物は中間処理に手間がかかり、処理費用が割高になるでしょう。また、混合された廃棄物は再資源化の対象とならず、結局は焼却や埋立処分となってしまい、費用対効果が低下するリスクもあります。
マニフェスト関連費

産業廃棄物を適正に処理する上で欠かせないのが、マニフェスト制度です。マニフェスト制度においては、廃棄物の排出から最終処分までの流れを記録・管理することが義務付けられています。
紙マニフェストや電子マニフェスト(JWNET)を使用する際には、それぞれ事務手続きやシステム利用に関する費用が発生します。具体的には、以下の費用です。
- マニフェストの発行・管理・記録にかかる人件費
- 電子システム利用料
- 業者ごとの事務手数料
特に排出量が多く、複数業者と取引している場合は、管理工数も増加し、見えづらいコストが積み上がっていきます。
このようなマニフェスト関連費を抑えるには、帳票管理のデジタル化や、業務フローの効率化が不可欠です。さらに、計量機やはかりを活用して廃棄物の種類や量を自動記録する仕組みを導入すれば、記載ミスの削減や入力時間の短縮にもつながります。
産業廃棄物の処理コスト一覧

産業廃棄物にはさまざまな種類があり、それぞれに応じた処理方法が必要です。そのため、処理にかかるコストも廃棄物の性質によって異なります。具体的には、以下の通りです。
| 廃棄物の種類 | 処理方法例 | 単価の目安(円/kg) |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 焼却処理 | 約30〜60 |
| プラスチック類 | 焼却・リサイクル | 約40~80 |
| 金属くず | 再資源化(売却含む) | 約0〜-20(売却可能) |
| ガラス・陶磁器類 | 埋立処分 | 約50〜100 |
| 紙くず | 焼却・リサイクル | 約10~30 |
| 木くず | 焼却・破砕処理 | 約20~50 |
| 汚泥 | 脱水・焼却・埋立 | 約100〜200 |
| 廃油 | 焼却・再資源化 | 約50~150 |
| 廃酸・廃アルカリ | 中和・無害化処理 | 約100〜300 |
同じ種類の廃棄物であっても、含水率や混合物の有無によって処理単価が変動するケースもあります。
上記はあくまで目安であるため、まずは現状の排出データを正確に把握することから始めましょう。不要な廃棄物の削減や、再資源化可能な廃棄物の見直しを行うことで、トータルコストの削減につなげることが可能です。
廃棄物の処理コストを左右する要因

製造現場で発生する廃棄物の処理コストは、単純な量だけでなく、さまざまな要因によって変動します。具体的には以下の要因が影響しており、これらの条件を踏まえずに処理を委託してしまうと、想定以上の費用負担が発生することもあります。
それぞれの要因について解説していきます。
廃棄物の種類

廃棄物の種類は、処理コストに最も影響を与える要因です。可燃ごみや紙くずなどの一般的な廃棄物は比較的安価に処理できますが、汚泥、廃油、廃酸といった特別管理産業廃棄物に分類されるものは処理費用が高額になります。
また、同じ種類でも内容物によって単価が変動するケースがあります。例えば、プラスチック類でもPVC(塩化ビニル系)は燃焼時に塩素ガスを発生するため、処理費用が上がる傾向にあります。
金属くずのように、リサイクル価値のある廃棄物は逆に処理費がかからず、売却益が出ることもあるでしょう。
処理量・排出頻度

処理量と排出頻度は、廃棄物処理費用に大きく影響します。基本的に、廃棄物の量が多いほど処理コストも増加しますが、同時にスケールメリットが働く場合もあり、一定量をまとめて処理すれば単価が抑えることも可能です。
一方で、少量でも高頻度に排出されると、収集回数が増えることで運搬費が嵩み、割高になるケースがあります。特に、定期契約を結んでいる業者としては、排出頻度が処理スケジュールに影響を与えるため、適正な回収頻度の設定が重要です。
廃棄物の量や発生サイクルを把握するためには、日常的な排出管理が必要不可欠です。特に多品種少量生産の現場では、排出のばらつきを定量的に把握することがコスト管理のポイントになるでしょう。
運搬距離

廃棄物を処理施設まで運ぶ距離が長くなると、その分運搬コストが上昇します。運搬距離には、処理場との物理的な距離だけでなく、以下の要因も影響します。
- 道路事情
- 交通状況
- 回収ルートの効率性
例えば、都市部では距離が短くても渋滞により輸送時間が長くなることで、費用が割高になるケースも想定されます。
特別管理産業廃棄物を運搬する場合は、専用車両が必要となり、追加の費用が発生する場合もあります。積載量に無駄があると回数が増え、運搬費の総額がかさむ原因にもなるでしょう。
対策としては、廃棄物の圧縮や容器の適正化や、計量機による発生量の定量管理が効果的です。
分別精度

分別の精度は、処理工程全体のコストに大きな影響を与えます。分別が不十分な廃棄物は、中間処理の手間が増えたり、再資源化できるはずの資源が混合により焼却・埋立されることになったりするため、処理単価が上がります。
また、誤った分別は処理業者側の対応負荷を増やし、追加費用が発生するケースもあります。混入禁止物や危険物が含まれていた場合、受け入れを拒否されることもあるため、注意が必要です。
地域・行政ごとの規制

廃棄物処理に関する規制は、自治体ごとに異なるケースがあり、これもコストに大きく影響する要因です。地域によっては分別基準が厳しく、特定の廃棄物に関しては再資源化が義務付けられていたり、特別な処理方法を求められたりすることがあります。
また、処理業者の数や施設の整備状況も地域によってばらつきがあるため、同じ処理内容でも地域によって単価が異なることがあります。加えて、条例による廃棄物の排出回数制限や時間指定がある場合、追加コストが発生することも考えられるでしょう。
このような地域特性を考慮しないまま全国一律の対応をしてしまうと、思わぬコスト増につながるリスクがあります。地域規制に関する情報は、自治体の公開資料や契約業者からの情報提供をもとに、定期的に確認しましょう。
製造現場で廃棄物コストを下げるアプローチ手法

製造現場における廃棄物の処理コストは、「下げる」ことを意識して取り組むことで削減が可能です。具体的なアプローチ手法としては、以下のようなものがあります。
それぞれのアプローチ手法について解説していきます。
廃棄物の減量化
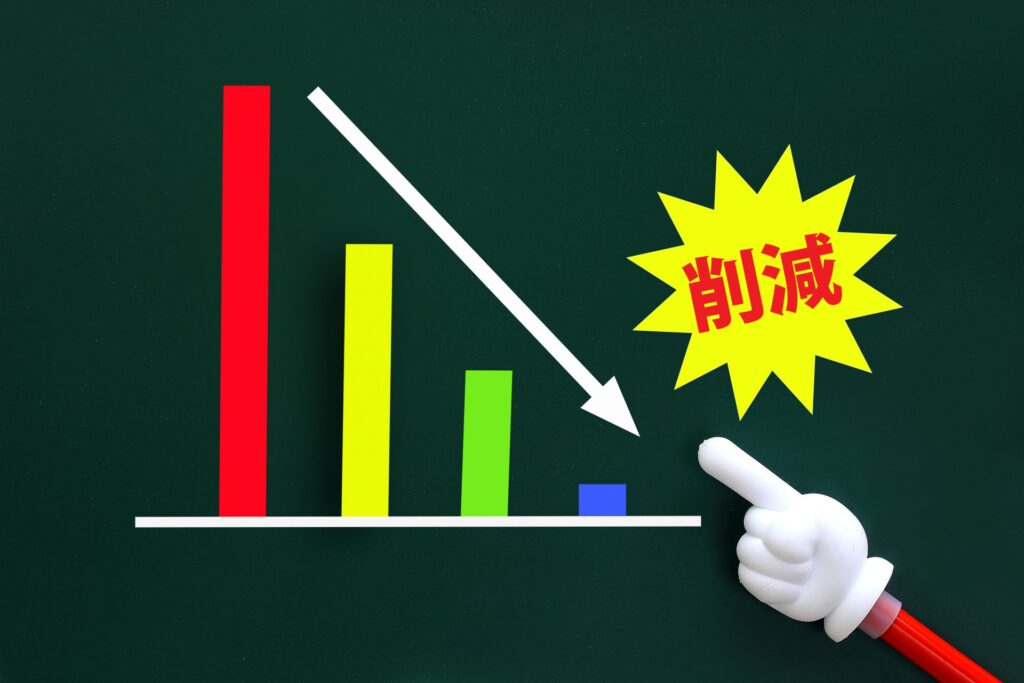
廃棄物処理コストを削減するための最も効果的な方法は、「そもそも廃棄物を出さない」ことです。製造工程の中で発生する端材、不良品、包装材などの見直しを通じて、不要な廃棄物の発生そのものを抑えることが重要です。
例えば、原材料の歩留まりを改善することで、端材や残渣の排出量を削減できます。また、工程管理を徹底することで、不良品率の低下にもつながり、再加工や廃棄のコストが軽減されます。さらに、包装材を過剰に使用している場合は、仕様を見直すことで資材コストと同時に廃棄コストも削減可能です。
これらの取り組みを継続的に行うには、日々の排出量を定量的に把握する仕組みが必要です。はかりや計量機を用いて廃棄物の種類別・工程別の排出データを記録することで、減量化の成果を可視化し、PDCAサイクルを回しやすくなります。
分別精度の向上

廃棄物の分別精度を高めることは、処理コストの抑制と、再資源化率の向上の両面で効果を発揮します。
混合廃棄物は処理業者側での分別負担が増えるため、割高な中間処理費がかかりやすくなります。また、再利用可能な資源が混ざってしまうと、せっかくのリサイクルの機会が失われることでしょう。
現場での分別精度を向上させるには、明確な分別ルールの策定が不可欠です。廃棄物の分類表示や色分けされた専用容器の設置など、視覚的な工夫も有効です。また、従業員の意識を高めるために、定期的な研修やポスター掲示、排出データの共有も重要になります。
再資源化・リサイクルの推進

再資源化の推進は、廃棄物の処理費を抑えるだけでなく、資源の有効活用と環境負荷の軽減にも貢献する効果的なアプローチ手法です。
廃棄物の中には、金属くずや紙、プラスチックなど、リサイクル可能なものが多く含まれています。これらを適切に分別・排出することで、再資源化ルートに乗せることができ、処理費の削減や逆に売却益を得られる可能性もあります。
ただし、再資源化を行うためには一定の品質が求められるため、排出段階での分別と混入防止がポイントです。異物が混ざった資源はリサイクル困難となり、通常の廃棄物と同様に処理費がかかってしまうこともあります。
そのため、定量管理によって排出内容の記録を活用し、継続的に再資源化率をモニタリングすることが効果的です。また、再資源化に対応した業者と提携することで、資源循環型の運用がスムーズに進みやすくなります。
委託業者の見直しと比較選定
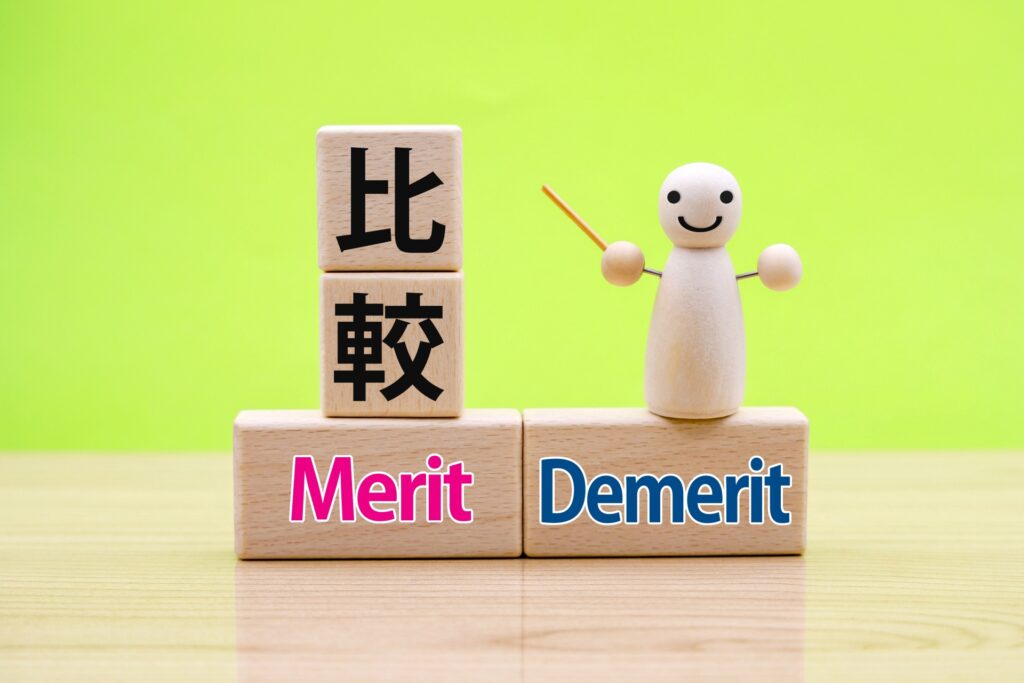
契約している廃棄物処理業者の費用や対応内容を見直すことも、コスト削減に直結するポイントです。同じ種類・量の廃棄物でも、処理業者によって料金体系やサービス内容に差があるため、定期的な見積もり比較が推奨されます。
契約内容が古いまま継続されている場合、廃棄物の実情に合っていない処理方法が採用されており、無駄な費用がかかっているケースもあります。そのため、以下の要素を多角的に評価して再検討を行うことが必要です。
- 契約単価
- 回収頻度
- 処理方法
- マニフェスト対応の柔軟性
見直しの際には、自社で収集した廃棄物の排出データが交渉材料として有効に機能します。計量による定量データや排出傾向の分析資料があれば、合理的な条件での契約交渉が可能です。
【業界別】廃棄物削減でコスト削減と利益アップを実現した事例

廃棄物の削減は、製造業をはじめとする以下の業界で取り組まれています。
業界ごとのアプローチは異なるものの、それぞれが成果を出しており、廃棄物の削減が推進されています。各業界での取り組みについて詳しく解説していきます。
製造業:端材の再利用と回収フロー見直し

ある金属加工メーカーでは、工程ごとに大量の金属端材が発生しており、そのほとんどが混在した状態で廃棄されていました。処理業者からの中間処理費用や運搬費が高騰していたことから、端材の再利用と回収フローの改善に着手しました。
まず、端材の種類ごとに分別する回収ステーションを構築し、素材ごとに再資源化できる体制を整備。次にはかりを導入し、部署別に端材排出量を記録することで、どの工程で無駄が発生しているかを数値で把握できるようになりました。
その結果、再利用率が大幅に向上し、一部の金属くずは逆に売却益が出るように。加えて、不要な回収回数が減ったことで運搬費も削減され、年間で約20%の処理コストカットを実現しました。
食品加工:生ごみ削減と作業標準化

食品加工業では、生ごみの多さが大きな課題とされています。
ある冷凍食品メーカーでは、原材料の過剰仕入れや加工時の歩留まりの悪さから、大量の食品廃棄が発生していました。これに対し、まず仕込み作業の標準化を徹底。無駄のない食材カット手順を明確にし、従業員ごとのばらつきを減らしました。
さらに、計量機を活用して日ごとの生ごみ排出量を計測し、現場スタッフに数値をフィードバックすることで部署単位での廃棄目標を掲げ、現場の意識も向上しました。
これにより、原材料の仕入れ量を10%削減できたほか、生ごみの排出量も15%減少。処理費だけでなく、原価率の改善にもつながり、利益率の向上を実現しました。
物流:梱包材料見直し

物流業界では、配送時の梱包材が大量に使用され、その多くが使い捨て廃棄物となっています。ある倉庫事業者では、緩衝材や段ボールのコストが高騰していたため、梱包材の再利用と仕様見直しに取り組みました。
具体的には、商品別に必要な緩衝力を再評価し、過剰な梱包を削減に着手したそうです。再利用可能な通い箱やリターナブル容器を一部導入し、使い捨て資材の使用を抑えました。
その結果、梱包材の購入コストが年間で12%削減されたほか、廃棄物として処理される量も大幅に減少。処分費と資材費の両面から利益改善に成功しました。
工場:分別強化

ある電子機器の製造工場では、全社的に廃棄物コストの削減を目的とし、分別体制の強化を実施しました。それまで可燃・不燃の大まかな区分しかなく、リサイクル可能な金属やプラスチックも混合廃棄されていたことが、コスト増加の原因となっていたようです。
分別強化では、廃棄物の種類ごとに専用容器を設置し、分別ルールを明確化。現場ごとの排出量を計量機で記録し、分別が不適切な部門には再指導を行う仕組みを整えました。
これにより、再資源化率が向上し、廃棄物全体のうち約30%を有価物として再利用を可能に。また、中間処理業者からの処理費見直しにもつながり、年間で数百万円規模のコストダウンを実現しました。
飲食チェーン:店舗廃棄物の見える化と分別

全国展開している飲食チェーンでは、店舗ごとに発生する食品廃棄や包装資材ごみの処理費が課題となっていました。特に、店舗単位での廃棄物管理が属人的であり、改善余地が見えづらい状況でした。
そこで、各店舗に小型のはかりを導入し、日ごとの廃棄量を記録・報告させる体制を整備しました。これにより、廃棄傾向が「数値」で可視化され、店舗間の比較も可能となりました。
さらに、店内での分別指導を徹底し、プラスチック容器や段ボールの再資源化も推進。本部がまとめて契約していた処理業者に対し、分別状況を共有することで処理単価の見直し交渉にも成功しました。
おすすめの全自動組み合わせはかりメーカー3選

製造現場や包装ラインで使用される「全自動組み合わせはかり」は、廃棄物削減とコスト効率化を両立できる機器です。特に、包装原料や内容物の計量において、過剰充填を防ぎながらも高い生産性を実現するため、多くの現場で導入が進んでいます。
以下では、全自動組み合わせはかりを提供するおすすめの国内メーカーを3つ紹介します。
導入を検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。
大和製衡株式会社

大和製衡株式会社(Yamato Scale)は、国内トップクラスのはかりメーカーであり、全自動組み合わせはかりの分野においても高いシェアを誇ります。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 大和製衡株式会社 |
| 住所 | 〒673-8688(〒673-0849) 兵庫県明石市茶園場町5番22号 |
| 電話番号 | 078-918-5526 |
| 公式HP | https://www.yamato-scale.co.jp/ |