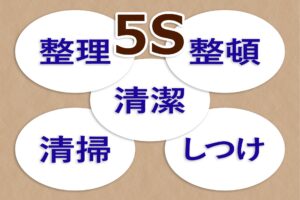食品工場での歩留まりの低下は、見過ごすと生産コストの増加や納期遅延を招く重大なリスクとなります。しかし、その根本となる原因を把握していなければ、解決は見込めません。
そのため、歩留まりの原因を把握し、的確に対処することで、劇的な改善が見込めます。原因がはっきりすれば、歩留まり低下を解決するためのアプローチ手法も明確になるはずです。
本記事では、食品工場で歩留まりが低下する原因や改善方法、改善によって期待できる効果をご紹介します。現場の歩留まりに悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
また、以下ではおすすめの組み合わせはかりメーカーについて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
食品工場における歩留まりとは?

食品工場における「歩留まり」とは、投入した原材料に対して最終的に製品として出荷できた割合を示す指標です。この数値は、生産効率やコスト管理に直結する重要な要素であり、企業の収益性を大きく左右します。
原材料費の高騰や人件費の増加が続く中、歩留まりの改善は食品製造現場において最優先課題のひとつとなっています。
ここでは、食品工場で歩留まりがなぜ重要なのか、その基本的な考え方や計算方法をわかりやすく解説します。
これらの指標を正しく理解することで、生産工程の改善やコスト削減につながる「見える化」が可能になります。以下で詳しく解説します。
食品工場で歩留まりが重要な理由
食品工場では、原材料を加工して最終製品に仕上げる過程で、加工ロス・カットロス・加熱による減量などが発生します。これらのロスを最小限に抑えることが、歩留まりを高めるうえで重要です。
歩留まりが改善されると、同じ原材料量からより多くの製品を生産できるため、原価率の低下と利益率の向上につながります。
また、製造ラインの効率化や品質の安定にも寄与します。特に、食品工場は原料コストの割合が高いため、歩留まりの管理は経営の安定に欠かせない要素です。
歩留まり率とは?計算方法
歩留まり率とは、投入した原材料のうち、どれだけが製品として完成したかを示す割合です。計算式は以下の通りです。
歩留まり率(%)=(製品重量 ÷ 原材料重量)×100
たとえば、100kgの原材料から80kgの製品ができた場合、歩留まり率は80%となります。
この数値を定期的に測定することで、どの工程でロスが発生しているかを把握しやすくなります。
食品工場では、製品種類ごとに歩留まり率を記録・比較することで、改善効果の検証や品質維持にも活用されています。
良品率とは?
良品率とは、製造された製品のうち、検査を通過して出荷可能な「不良のない製品」の割合を指します。計算式は以下の通りです。
良品率(%)=(良品数量 ÷ 総生産数量)×100
良品率は品質管理の指標として使われ、工程内の不良や異物混入などを数値で評価できます。歩留まり率が「原材料から製品になる効率」を示すのに対し、良品率は「製品の品質水準」を表すものです。
両方を併せて管理することで、食品工場全体の生産効率と品質の最適化が可能になります。
食品工場で歩留まりを改善すると具体的にどう変わる?

食品工場で歩留まりを改善すると、原材料コストの削減や生産効率の向上、利益率の改善など、経営全体に大きな影響を与えます。特に食品製造では原材料費の割合が高く、わずか数%の改善でも年間で見ると非常に大きな成果を生み出します。
ここでは、歩留まりを5%改善した場合の具体的なシミュレーションを紹介します。
歩留まりを5%改善した場合のシミュレーション表
| 項目 | 改善前 | 改善後 | 差(効果) |
|---|---|---|---|
| 原材料投入量 | 1,000kg | 1,000kg | — |
| 歩留まり率 | 90% | 95% | +5% |
| 製品生産量 | 900kg | 950kg | +50kg |
| 原材料単価 | 500円/kg | 500円/kg | — |
| 原材料コスト | 500,000円 | 475,000円 | ▲25,000円/日 |
| 年間削減額(稼働360日) | — | — | 約900万円削減 |
このように、歩留まり率を90%から95%に改善するだけで、年間約900万円の原材料費削減が可能になります。
また、原材料ロスが減ることで処理・廃棄にかかるコストも軽減され、同じ投入量でより多くの製品を生産できるため、生産効率も向上します。歩留まりが改善されると、生産ラインの安定稼働が実現し、製造リードタイムの短縮やエネルギー使用量の削減も可能です。
結果として、利益率の向上だけでなく、環境負荷の低減や品質の安定といった副次的なメリットも得られます。
このように、わずかな歩留まり改善でも食品工場にとっては大きなインパクトがあり、「コスト削減」+「生産性向上」+「品質維持」を同時に実現できる有効な施策といえるでしょう。
そもそも食品工場で歩留まりが低下する主な原因は?
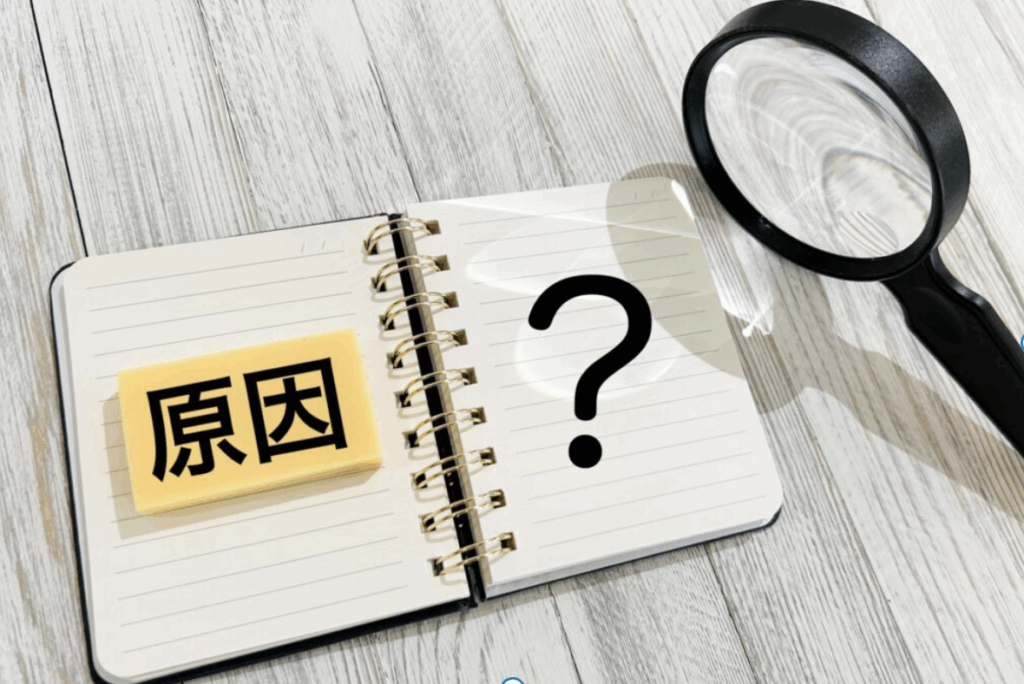
食品工場における歩留まりの低下は、原材料ロスの増加や生産コストの上昇を招き、利益率を大きく圧迫します。特に食品製造では「原料・設備・人・環境」など多くの要因が絡み合うため、原因を特定して対策することが重要です。
ここでは、食品工場で歩留まりが低下する主な原因を5つに分けて解説します。
これらの原因を把握することで、どこに改善の余地があるかを明確にし、効果的な歩留まり改善につなげることができます。以下で詳しく解説します。
設備や機械の不具合・老朽化
食品工場では、計量機やミキサー、カッターなどの設備に不具合が生じると、原材料の過剰投入や加工ミスが発生しやすくなります。特に、はかりや自動充填機のセンサー精度が低下している場合、重量誤差が積み重なり歩留まりの悪化につながるので注意が必要です。
また、老朽化した機械は停止や異常運転が起こりやすく、生産効率にも悪影響を及ぼします。定期点検やキャリブレーションの実施、IoTを活用した稼働監視によって、設備の状態を見える化し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
原材料の品質ばらつき
食品製造では、原材料の品質差が歩留まり低下の大きな要因になります。産地・季節・仕入れロットによって水分量や形状が変化すると、加工工程での歩留まり率にも影響します。
特に生鮮食品では、異なるサイズや鮮度によってカットロスや加熱ムラが発生することがあるので注意が必要です。仕入れ段階での品質基準の明確化や、原料のトレーサビリティ管理を徹底することが有効です。
また、原材料の性質を分析してレシピや加工条件を調整するなど、事前対策が求められるでしょう。
作業者のスキル不足や作業ミス
作業員によるカット精度の違い、投入量のばらつき、手作業工程での判断ミスなども歩留まり悪化の原因です。特に食品工場では、人の手作業が多い工程でロスが発生しやすく、経験や勘に頼った作業では再現性が低下します。
改善策としては、作業手順の標準化やマニュアル整備、トレーニングによるスキル向上が効果的です。
また、組み合わせはかりや自動計量機を導入し、作業の自動化・精度向上を図ることで、人為的ロスを削減できます。人的要因をデータで管理する仕組みづくりも重要です。
製造工程設計や管理体制の不備
工程設計や管理が不十分な場合、材料の滞留や過剰生産、温度・湿度条件の不適切管理によってロスが発生します。
食品は品質劣化しやすく、加工や保管のタイミングを誤ると廃棄率が上がり、結果的に歩留まりが低下します。したがって、歩留まり改善のためには、工程ごとの投入量・加工時間・生産量を可視化し、データに基づいた改善が欠かせません。
生産計画と実績の差異を分析し、無駄を最小化するPDCA体制を構築することで、安定した生産が可能になります。
外部環境やロット変動の影響
気温や湿度、季節変動などの外部環境も食品の歩留まりに影響を与えます。例えば、夏場は温度上昇により発酵や酸化が進みやすく、冬場は水分量の変化で乾燥ロスが起こるケースがあります。
また、仕入れロットごとの原料差や製造ラインの切り替えによる歩留まり変動も見逃せません。
環境モニタリングやロット別データの蓄積を行い、歩留まり変化の傾向を定量的に把握することが必要です。AIやIoTセンサーを活用したリアルタイム監視によって、外的要因によるロスを最小限に抑えることができるでしょう。
食品工場で歩留まり低下を改善する方法!6選

食品工場で歩留まりが低下すると、原材料費の増加や生産コストの上昇につながり、最終的には利益率を圧迫します。そのため、歩留まり改善は製造現場における「品質・コスト・生産性」すべてを高める取り組みとして欠かせません。
ここでは、現場で実践しやすく、効果が得られやすい歩留まり改善の方法を6つ紹介します。
これらの施策を組み合わせて実践することで、持続的に高い歩留まりを維持することができます。以下で詳しく解説します。
工程の見直しと作業標準化
歩留まり改善の第一歩は、製造工程を見直し、作業手順を標準化することです。同じ作業でも担当者によって手順や精度が異なると、製品品質や原料使用量にばらつきが生じます。
手順書やマニュアルを整備し、作業内容を明確にすることで、ロスの発生を防止できます。
また、工程ごとにロスが出やすい箇所を特定し、投入量や加工条件を最適化することも重要です。標準作業を徹底することで、再現性の高い生産が可能になり、安定した歩留まりが確保されます。
設備・機械の保守点検と最適化
設備の不具合や精度低下は、歩留まり低下の主な原因のひとつです。特に、はかりや充填機、包装機などの精度がずれると、原料の過剰投入や欠品が発生しやすくなります。
定期的な点検とキャリブレーションを行い、正常な稼働状態を維持することが大切です。また、老朽化した設備は省エネ型や高精度タイプに更新することで、長期的なコスト削減にもつながります。
設備トラブルを未然に防ぐため、IoTによる稼働監視やメンテナンス計画の自動化も有効です。
原材料の品質管理とロス削減
原材料の品質ばらつきは、食品工場における歩留まりの変動要因です。入荷時の検査基準を厳格化し、原料ロットごとのデータを記録・分析することで、品質の安定化を図れます。
また、原料カットや混合時のロスを削減するために、自動計量システムの導入も効果的です。不良原料や廃棄ロスを減らすことで、全体的な生産コストを抑えつつ、安定した製品供給が可能になります。
品質管理体制を強化することは、歩留まりだけでなく製品の信頼性向上にも直結するでしょう。
人材教育と技能継承の強化
作業員の熟練度や知識不足によるミスも、歩留まりを悪化させる原因です。経験者と新人で作業精度に差が出るのを防ぐため、教育体制を整備し、技能継承を仕組み化しましょう。
動画マニュアルやデジタル指示書を活用すれば、手順を誰でも正確に再現できます。
また、歩留まりに関するデータを共有し、現場全体で改善意識を高めることも重要です。人材の育成と情報共有を進めることで、作業のばらつきが減り、安定した製造品質を維持できます。
データ分析による歩留まり要因の可視化
歩留まりを定量的に管理するには、データ収集と分析が欠かせません。工程ごとの投入量・製品量・廃棄量をリアルタイムで記録し、歩留まりの変動を数値で把握します。これにより、ロスが発生している工程や原因を客観的に特定することが可能です。
また、ExcelやBIツール、IoTセンサーなどを活用した「見える化」を進めることで、改善活動の精度が向上します。データに基づく分析は、勘や経験に頼らない効率的な歩留まり改善を可能にします。
自動計量・IoT機器の導入による精度向上
最新の自動計量機や組み合わせはかりを導入することで、原材料の過剰投入や欠品を防止できます。IoT機器と連携することで、計量データを自動記録・分析し、歩留まりの変化をリアルタイムで把握することもできるでしょう。
また、AIによる予測分析を組み合わせれば、異常値や不具合の早期検知も可能です。特に食品工場では、製品ごとに投入量や粘度が異なるため、精度の高い計量機がロス削減に大きく貢献します。
自動化とデジタル化を進めることで、人為的ミスを最小限に抑え、継続的な歩留まり向上が実現します。
歩留まり改善によって得られる効果

歩留まりを改善することは、単に不良品を減らすだけではありません。製造現場全体に波及効果をもたらし、コスト削減・品質向上・納期遵守といった多方面の成果につながります。具体的な効果としては、以下の通りです。
それぞれの効果について解説していきます。
製造原価の圧縮

歩留まりが改善されることで、最も顕著に現れるのが製造原価の削減です。不良品が減るということは、それだけ原材料や部品、作業時間の無駄が削減されることを意味します。
また、原価の削減に伴い加工途中でのロスや再加工による手間が減るため、人件費やエネルギーコストの面でもメリットがあります。特に高価な原材料や部品を使用している場合、歩留まりの向上はダイレクトに利益に直結するでしょう。
さらに、製造原価が安定することで、価格競争力のある製品づくりが可能となり、市場での競争優位性を高める要因にもなります。継続的な歩留まり改善によって、製品ごとのコスト構造を最適化できれば、収益体質の強化にもつながります。
不良品対応の削減
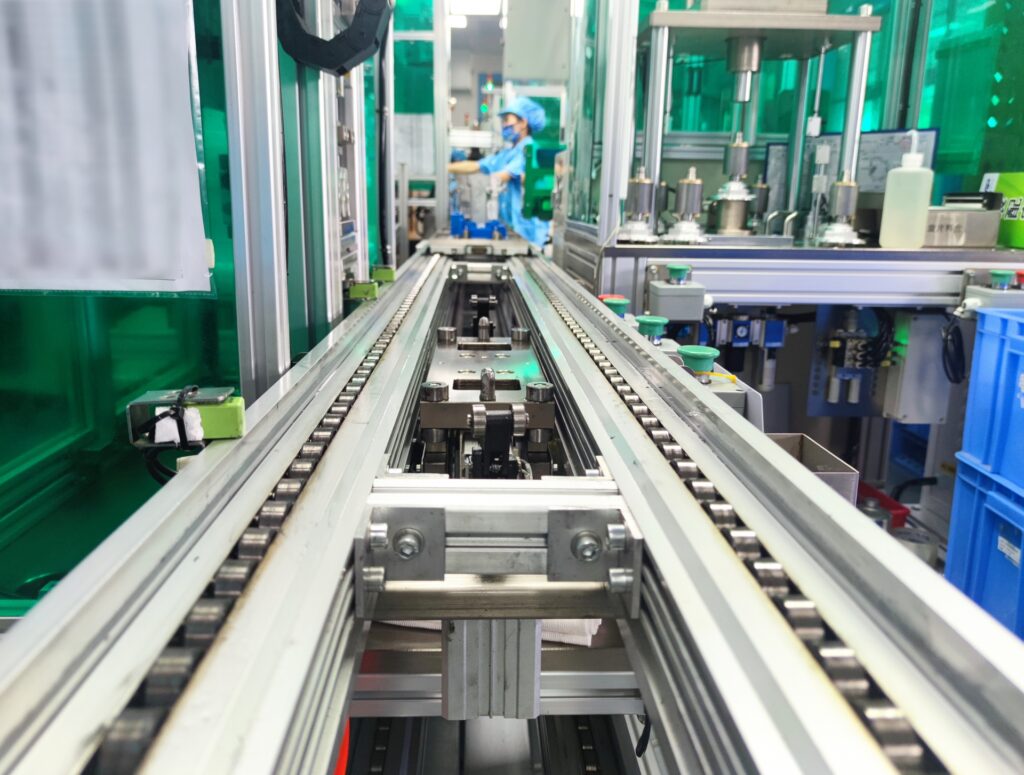
歩留まりの向上は、不良品発生に伴う対応工数の削減にも寄与します。不良品が発生した場合には、原因調査・再製造・報告書作成・取引先への連絡といった対応が必要になりますが、これらの業務は本来の生産活動とは直接関係なく、企業にとっては非効率なコストです。
また、顧客からのクレームや返品が発生すれば、信頼の低下や売上損失といった二次的な影響も避けられません。歩留まりが高い状態を維持できれば、こうしたリスクを回避でき、品質に対する安心感を顧客に与えることが可能です。
納期遵守率・供給安定性の向上

歩留まりの改善は、納期の遵守や製品供給の安定化にも貢献します。
歩留まりが低下している現場では、不良品の再製造や再検査に時間を要し、予定通りに出荷できない事態に陥りがちです。これによって納期の遅延や計画変更が頻発し、顧客からの信頼を損なうリスクが高まります。
一方で、歩留まりが安定していれば、予定通りの数量を確保しやすく、無駄なリードタイムの発生も抑えられます。結果として生産スケジュールが守られやすくなり、納期遵守率が向上するでしょう。
特に、ジャストインタイムを重視する取引先に対しては、安定供給の実現が大きな強みとなります。さらに、急な追加注文やトラブル発生時にも対応できる生産余力が生まれるため、ビジネスの拡大や新規受注にもつながります。
設備稼働効率の向上

歩留まりの向上は、設備の稼働効率(OEE)にも直接影響を与えます。不良品の発生率が高いと、ライン停止や再加工のための段取り替え、調整作業が必要となり、設備の稼働時間が減少してしまうでしょう。これにより、せっかくの高性能な機械も能力を十分に発揮できない状態に陥ります。
一方で、歩留まりが改善されると、ラインがスムーズに流れ、停止時間が減少します。また、品質不良による作業中断や不具合対応の頻度が減ることで、全体の稼働率が向上します。生産能力の最大化を図るうえで、歩留まりの改善は重要な指標です。
さらに、稼働率が向上すれば、同じ時間・同じ設備でより多くの製品を製造できるため、設備投資の回収期間短縮やROIの向上にもつながります。
食品工場の歩留まり改善にはなにがおすすめ?
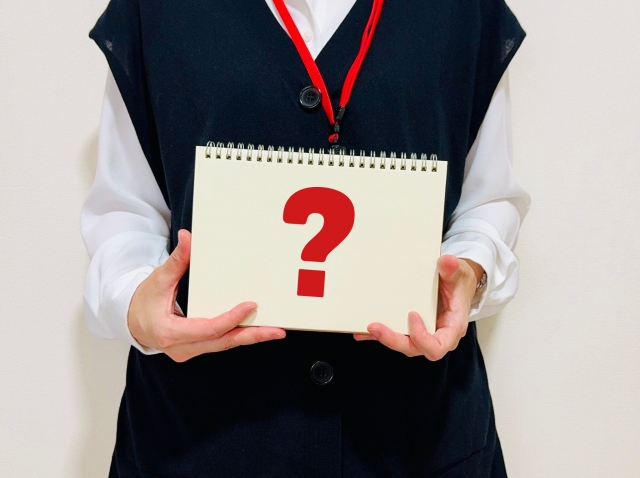
食品工場で歩留まりを改善するには、現場の状況を正確に把握し、ロスの発生源を定量的に管理する仕組みが欠かせません。
特に、原材料ロスや計量誤差を最小限に抑えるためには、「正確な計量」と「工程の見える化」がカギとなります。これらを実現するためには、人の勘や経験に頼るのではなく、デジタル技術や自動化機器を積極的に導入することが効果的です。
ここでは、食品工場の歩留まり改善におすすめの方法を紹介します。
これらの施策をバランスよく取り入れることで、無駄を減らしつつ高品質・高効率な生産体制を構築できます。以下で詳しく解説します。
自動計量システムや組み合わせはかりの導入
歩留まり改善に最も効果的な手段のひとつが、自動計量機や全自動組み合わせはかりの導入です。従来の手作業では、投入量の誤差や過剰充填が起きやすく、原材料ロスの原因となっていました。
全自動組み合わせはかりを導入すれば、製品ごとに最適な重量を自動で計算・組み合わせし、計量精度を大幅に向上することが可能です。
さらに、IoT連携によって計量データをリアルタイムで収集・分析すれば、歩留まり率の変化を可視化し、改善効果を数値で管理することもできます。食品工場では、正確な計量が「品質」と「コスト削減」を両立させる第一歩となります。
データ分析によるロス要因の特定と改善
歩留まりの低下要因は、工程ごとに異なります。そのため、現場データを分析してロスの発生ポイントを特定することが重要です。
生産ラインの投入量・加工量・廃棄量を定期的に記録し、歩留まり率を数値で把握することで、どの工程に無駄があるかを明確にできます。
また、BIツールやAIを活用して過去データから傾向を分析すれば、トラブルの予兆検知や最適条件の設定も可能です。勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた改善を行うことで、持続的かつ安定した歩留まり向上が実現します。
現場教育と作業標準化の徹底
歩留まり改善を長期的に維持するには、現場スタッフの理解とスキル向上も欠かせません。
作業ミスやばらつきを防ぐために、作業手順の標準化と教育の仕組み化を進めましょう。
たとえば、動画マニュアルやデジタル作業指示書を活用すれば、誰でも一定の精度で作業を再現できます。
また、歩留まり率をKPIとして共有し、スタッフ全員が改善目標を意識することも効果的です。「設備の精度 × 人の意識」を両立させることで、ロスの少ない持続的な生産体制を実現できるでしょう。
自動計量システムや組み合わせはかりを導入する際の注意点

食品工場で歩留まりを改善するために、自動計量システムや全自動組み合わせはかりの導入は非常に効果的です。しかし、導入時の検討が不十分だと「思ったほど成果が出ない」「運用コストが増加した」などの問題が起きることもあります。
正しく導入するためには、現場の運用環境や目的に合わせた計画的な準備が必要です。
ここでは、自動計量機や組み合わせはかりを導入する際に押さえておくべき3つの注意点を紹介します。
これらを意識して検討すれば、導入後のトラブルやコストの無駄を防ぎ、安定した生産効率向上が期待できます。以下で詳しく解説します。
現場環境や製造ラインに適した機種を選ぶ
自動計量システムや組み合わせはかりは、製品の種類・重量・形状によって最適なモデルが異なります。たとえば、粉体・液体・個包装食品ではそれぞれ計量精度や搬送方式の設計が違うため、汎用型では対応できない場合があります。
導入前には、ラインの搬送速度や設置スペース、作業環境(湿度・温度・防塵条件など)を正確に確認することが重要です。
また、製造ライン全体との連携も考慮し、上流・下流機器との通信性が高いシステムを選ぶことで、歩留まりの最適化と生産効率の両立が可能になります。
導入後の運用・メンテナンス体制を確認する
導入後の安定稼働を維持するためには、メーカーや販売代理店によるメンテナンス・サポート体制を事前に確認することが欠かせません。
食品工場では長時間稼働や多品種切り替えが多いため、トラブル時の対応スピードや保守契約の内容が歩留まりに直結します。部品供給が迅速で、定期点検やキャリブレーション(校正)が容易なメーカーを選ぶことが望ましいでしょう。
また、操作教育やトレーニングプログラムが充実しているメーカーであれば、現場スタッフの習熟も早く、トラブルを未然に防ぐことができます。
複数社を比較検討して選ぶ
自動計量機や組み合わせはかりは、メーカーごとに得意とする分野や強みが異なります。一社だけの提案で決めてしまうと、機能・コスト・サポート面で最適な選択ができない可能性があるので注意が必要です。
したがって、複数社から見積もりを取り、精度・スピード・耐久性・保守コストを総合的に比較検討することが重要です。
特に、食品の種類や包装形態によっては、特定メーカーの機種が高い歩留まり改善効果を発揮する場合があります。複数メーカーの導入実績や事例を確認し、自社の生産条件に最も適した機種を選定することが、失敗しない導入への近道です。
失敗しない!全自動組み合わせはかりメーカーの選び方

全自動組み合わせはかりは、食品工場の生産性や歩留まりを大きく左右する重要な設備です。メーカーごとに設計思想や得意分野が異なるため、導入目的や現場環境に合わせた選定が求められます。
ここでは、より実践的な観点から、導入後に後悔しないための3つの選び方を紹介します。
これらの視点を押さえておくことで、現場に最も適したメーカーを選定しやすくなります。以下で詳しく解説します。
計量精度・処理スピード・清掃性をバランスで評価する
全自動組み合わせはかりの性能を判断するうえで重要なのが、計量精度・処理速度・清掃性の3点です。高精度でスピーディーな計量ができても、清掃に時間がかかれば生産効率が低下します。
食品工場では異物混入防止のために頻繁な洗浄が必要なため、工具不要で簡単に分解・洗浄できる設計が理想です。
また、原材料の種類や粒度によって精度が変わる場合があるため、実際にサンプル計測を行って比較すると確実です。性能の「バランス」に注目することで、長期的な安定稼働とコスト削減の両立が可能になります。
操作性とカスタマイズ対応力を確認する
操作性が悪いと、現場での使い勝手や教育コストが増加します。そのため、画面操作の分かりやすさや設定変更のしやすさも重視すべきポイントです。
また、食品工場では製品切り替えや包装仕様の変更が頻繁に発生するため、柔軟にカスタマイズできるメーカーが望まれます。制御ソフトの更新対応や既存ラインとの連携実績があるかもチェックしておきましょう。
実際のオペレーターが試運転できるメーカーであれば、導入後の運用トラブルを防ぐことができます。
導入実績・サポートエリアの広さをチェックする
メーカーの信頼性を判断するうえで、導入実績の多さとサポート体制の広さは重要な指標です。食品業界での導入事例が多いメーカーは、衛生基準や作業環境に精通しており、トラブル時の対応もスムーズです。
また、全国に拠点を持つメーカーであれば、地方工場でも迅速な修理・メンテナンスが可能です。
海外展開を行う企業の場合、現地サポートや多言語対応の有無も確認しておくと安心です。
信頼できるメーカーを選ぶことで、長期的なサポートを受けながら安定した生産体制を構築できるでしょう。
おすすめの全自動組み合わせはかりメーカー3選

歩留まり改善や生産効率の向上を実現する上で、全自動組み合わせはかりの導入は効果的です。特に食品や医薬品、部品などを正確かつスピーディーに計量・選別する現場では、組み合わせはかりの性能が製品の品質や生産スピードに直結します。
信頼性と実績に優れた全自動組み合わせはかりメーカーとして、以下の3社をご紹介します。
自社の課題に合ったメーカー選定の参考として、ぜひお役立てください。
大和製衡株式会社

大和製衡株式会社は、兵庫県明石市に本社を構える老舗の計量機器メーカーで、組み合わせはかり分野において高い技術力を誇ります。同社の組み合わせはかりは、食品業界をはじめ、医薬品・工業製品など幅広い分野で導入されています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 社名 | 大和製衡株式会社 |
| 住所 | 〒673-8688(〒673-0849) 兵庫県明石市茶園場町5-22 |
| 電話番号 | 078-918-5526 |
| 公式HP | https://www.yamato-scale.co.jp/ |
独自の重量演算アルゴリズムにより、計量スピードと正確さを両立しており、設定値に対する歩留まりの最適化も可能です。また、防塵・防水設計のモデルも充実しており、衛生管理が求められる現場でも安心して使用できます。
さらに、現場に即したカスタマイズ対応にも定評があり、工程に応じたライン設計や自動化との連携も柔軟に対応可能です。国内でのサポート体制も充実しており、導入後の保守や教育にも力を入れています。
また、全自動組み合わせはかりの導入をお考えの方は、一度の大和製衡株式会社ホームページを訪れてはいかがでしょうか。
以下の記事では、大和製衡株式会社の特徴や口コミ、導入事例などをさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。
株式会社イシダ

株式会社イシダは、京都に本社を構える総合計量機器メーカーで、全自動組み合わせはかりの分野において世界的なリーダー企業の一つです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社イシダ |
| 住所 | 〒606-8392 京都市左京区聖護院山王町44 |
| 電話番号 | 075-771-4141 |
| 公式HP | https://www.ishida.co.jp/ww/jp/ |
イシダの製品は、優れた操作性と高速・高精度な計量機能が特長です。マルチヘッド構造による組み合わせ演算により、歩留まりを最小限に抑え、材料の無駄を大幅に削減できます。
さらに、ライン全体の自動化・省人化を支援する多彩なオプションと、異物検査機や包装機とのシームレスな連携が可能です。アフターサービス体制も国内外に広がっており、トラブル発生時の迅速な対応が期待できます。
また、以下の記事では株式会社イシダの評判や特徴について紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
アンリツ株式会社

アンリツ株式会社は、通信機器メーカーとしてのイメージが強い企業ですが、実は検査機器や計量機器の分野においても高い実績を持っています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 社名 | アンリツ株式会社 |
| 住所 | 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1 |
| 電話番号 | 046-223-1111 |
| 公式HP | https://www.anritsu.com/ja-jp/ |
全自動組み合わせはかりでは、食品や医薬品などの現場に向けて、高性能なソリューションを展開しています。
アンリツの組み合わせはかりは、コンパクト設計でありながら、極めて高精度な重量演算を実現しており、スペースに制限のある生産ラインでも効率的に運用できます。また、自社開発のセンサー技術を応用した高感度な検出機能により、わずかな重量誤差も見逃しません。
さらに、トレース性の高い記録管理機能を搭載しており、歩留まり管理や品質保証の面でも強みを発揮します。小規模ラインから高負荷生産まで柔軟に対応可能な点も魅力で、現場ニーズに応じた多様な提案力を持つメーカーです。
また、以下の記事ではアンリツ株式会社の評判や特徴について紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
まとめ

歩留まりの低下は、製造現場におけるコスト増や品質不良、納期遅延といった深刻な課題を引き起こします。しかし、その原因を正しく把握し、工程・設備・人材・検査体制などを多角的に見直すことで、改善は十分に可能です。
特に全自動組み合わせはかりの導入は、計量精度と効率を両立させ、歩留まり改善に大きく貢献します。
本記事で紹介した内容をもとに、まずは自社の不良発生要因を整理し、改善すべきポイントを明確にしましょう。そして、改善策の実施と効果検証を繰り返すことで、安定した生産体制と高い品質の両立が実現できます。